
古代メソポタミアの粘土板からは楔形文字で、異性愛のみならず、男性同士の性愛が成就するよう願う、呪文ないし祈祷文がいくつか発見されている。
『もし同じ身分の男性と背後から交わるならば、
彼は同胞や仲間たちの間で傑出した者となるだろう』
『もし男の廷臣と性交するならば、彼は丸一年の間、災厄を免れるだろう』
『もし奴隷と男色するならば、心配事にとらわれるであろう』
ハンムラビ法典
「目には目を」の同害報復で名高いハンムラビ(バビロニア第一王朝六代目の王、在位前1792-50)の法典のどこにも男色を禁じる条文がない。先行するシュメールのウルカギナや、ウル・ナンムら(古代メソポタミアの支配者)の法典も同様である。
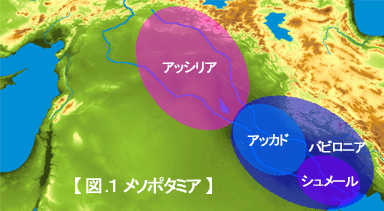
↑ティグリス川とユーフラテス川に挟まれたメソポタミアは肥沃な三日月地帯ともいわれる。
メソポタミアの南側にあるバビロニア地方のうち、ペルシャ湾岸沿いをシュメールという。
ただ、ハンムラビ法典には男色に関係すると想定される箇所が二、三、見出される。それは、通例「王の召使い」と訳されるギルセクムという名称の廷臣(宮廷に仕える臣下)に関する箇所である。
彼らギルセクムは、王宮や神殿などに所属する一種の侍従職ないし宦官(かんがん)だったと見なされている。ただ、宦官といえど必ずしも去勢されているとは限らないかったようだ。ギルセクムは妻帯を許されておらず、養子を迎えることを認められている特別な内官であった。「髭のない」と形容されるところから、国王の男色相手をつとめる若い寵臣(お気に入りの臣下)だったと一般に解釈されている。国王の寵童上がりで高位高官に上った内官というのも、古今東西の歴史上、その例が少なくないことは周知の事実である。
為政者に見初められた世話人が自らの体を売ることでフィクサーを陰で操る。それは女にも男にも等しく与えられた立身出世の機会で、ことに君主制ではかような背後に潜む性事情や愛憎劇に国の統治が揺らいでしまうこともあったといいます。城傾は絶世の美女を指す言葉ですが、城を傾かせたのが幼気な少年である場合もありました。同性愛者の自分としては、性に奔放で魅力的だけど、ワガママで自分の思い通りにならないとムキになる宦官の姿が思い浮かばれます(^^;
ヒッタイトの男色婚
小アジアにあったヒッタイト(前16-13世紀、オリエントを栄えたインド・ヨーロッパ語族系の民族。鉄器と馬を使用して軍事に優越し、小アジアからメソポタミア、シリア一帯を征服した)の首都ハットゥシャシュ(現在のポアズキョイ)の遺跡から出土した粘土板文書には、少なからぬ数の法典類が含まれている。

↑小アジアとは、黒海と地中海の間にあるアナトリア半島(現在のトルコ)のこと。
それらの法典の条文には、「男奴隷が結納金を贈るならば、自由身分の若者を娶って、その夫となること」を認めた法律があるという。
男性同士の婚姻を法制化したのは、ヒッタイト人をはじめとするオリエント諸民族の間に男色が広く普及していたからである。(この時代に同性婚があったとは!!)
奴隷でさえ、同性婚が法律で許されている以上、当然ながら自由身分の男性同士が結婚することはごく普通に行われていたに違いない。というよりも、この法文が制定されたのは、自由身分の男たちが同性同士で結婚したり、男色相手を金で手に入れたりするのは、極めて一般的な行為だったのでわざわざ明文化する必要はなかったが、男奴隷の場合は法の認可を要したため敢えてこのように書き記された、といったところが実状ではなかっただろうか。このヒッタイトの男色婚に関する法律は、のちにギリシアの立法者ソロンが作ったアテナイ法にも影響を及ぼすことになる。
近代以降の婚姻制度は権利義務関係に基づく話なので、それと比較して語るにはもう少し情報が必要なところではありますが、3000年以上も前に男性同士の結びつきについて成文法の根拠があったようです。男性に限れば、異性/同姓の区別より、封建的な身分の違いの方に社会的な差異があった様子が伺われます。
また、コミュニティの密度も濃かったと思われますから、構成員全員が何かしらの方法で子どもの養育に参加しているなど、夫婦と未婚の子で構成される現代の核家族とは違った家族観を共有していたのかもしれません。人の原点に近い古代史だからこそ、見えてくる性や家族の在り方ははなかなか興味深いものがあります。
ホモセクシャルの世界史に戻る




コメント